George LakoffとMark Johnsonによる
Philosophy In The Flesh
(1999, Basic Books)の翻訳である本書『
肉中の哲学―肉体を具有したマインドが西洋の思考に挑戦する
』で、まず題名の「肉中の」という語が気になるかもしれませんが、これはもちろん "in the flesh" (1. Alive; 2. In person; present) (
http://www.thefreedictionary.com/in+the+flesh)の訳語です。この語を訳者自身が「あとがき」で述べるように「生身の」と素直に訳し本書は
『生身の哲学』と訳しておけば、
アマゾンのカスタマーレビューでの翻訳への酷評は避けることができたのではないかと思います。私自身はこの翻訳をそれほどに酷いものとは思いません (たしかに英語をそのままカタカナで表記した語が多すぎますが)。むしろまだ私は英語を読むスピードが遅いので、この翻訳でまず全体像を把握し、重要箇所だけを原著で参照するやり方で、長い間未読だった本書をようやく読み終えることができました。
ちなみに「翻訳書を読むのは邪道だ」という意見もあるかもしれませんが、私は翻訳書と原著を読み比べることで、日本語と原語(本書の場合は英語)について深く考えることができ、自分の日本語を鍛えることができるので、興味深い本の翻訳書がある場合は、まずは原著読解とは比較にもならないスピードで日本語翻訳で読み、それから重要箇所を(あるいはすべてを)原著で読むという方法は悪い方法だとは思っていません(「英語ヲ勉強シナケレバ!」という思いから、長年なかなかこのようには思えませんでしたが、最近はこう思っています ―翻訳文化についてはいろいろ語りたいのですが、閑話休題。
ここではこの本を私なりにまとめます。といっても原著で624ページ、翻訳書で701ページですから、このまとめは非常に限定的で恣意的なものです。ここで扱われているトピックに興味を持たれた方は、必ず原著・翻訳書をご自身でお読みください。また以下で使う日本語翻訳は私で訳した日本語ですから、翻訳書とは異なる箇所もあります。(私はいつものように、日本語としての読みやすさを優先し、一部ではかなり意訳しています。また重要用語である"embodiment"はあえて「身体的形成」と訳しました。「身体化」という現在の定訳ではどうもわかった気になれなかったからです。 ― 乞御批判)。引用の末尾にあるページ数は原著のページ数を指します。
1 はじめに
この本の主張は、冒頭に書かれているように、次の三つの論点にまとめることができます。
心は、そもそも身体的に形成されたものである。
思考は、そのほとんどが無意識的なものである。
抽象概念は、概してメタファーにより構成されている。
The mind is inherently embodied.
Thought is mostly unconcsious.
Abstract concepts are largely metaphorical. (p. 3)
したがって、このまとめでは、まず上の三つの論点を(少し順番は変えて)概括し(「1 心の身体性」、「2 概念のメタファー性」、「3 思考の無意識性」)、次にこの概括から認知科学と西洋哲学を再検討する(「5 認知科学の特徴づけ」、「6 西洋的哲学伝統の再検討」、「7 哲学とはどうあるべきか」)という形でこの本をまとめます。最後に蛇足で私の考えを述べます(「8 雑考」)。
2 心の身体性
"Embodied mind"(「身体的に形成された心」)とは、「心は身体に即して形成された」ということを意味する表現です。実は、日本語文化伝統ではこの主張はそれほど奇異に思えないものかと思いますが、西洋的な学問を受け、そもそも日本語ですら明治以降かなり西洋化されてしまっていることになかなか気づかない現代日本人にとっても、この"embodied mind"の考え方は以下述べる西洋的伝統を有する人々と同様に、やや受け入れがたい表現・考え方に思えるかもしれません。「心 (mind) とは、身体 (body) と異なるものであり、心、特に心の抽象的な側面を語る際には、身体のことについて考える必要などはない」という考え方は、例えば現在、心理言語学に従事する多くの人にも共有されている考え方かと思います。いやそんな小難しい言い方をしなくとも「運動ばかりせずに勉強しなさい」といった言い方で、心の発達と身体の発達を相互排他的あるいはゼロサムゲームのように考える心と身体の二元論は私たちに染み付いているようです。ですが、レイコフとジョンソン(以下、著者)は、たとえばカテゴリーといった心の側面でさえ、身体を基盤に形成されたものであると考えます。
2.1 カテゴリーの身体性
著者は、カテゴリー化 (categorization) とは、「私たちがどのように私たちの身体で形作られているか」(how we are embodied) ということの進化の帰結であると述べます (p. 18)。なぜなら著者は、カテゴリー化を、人間以外の、神経機構を備えた生物 (neural beings)でさえも行うことだとしているからです。
どんな生き物もカテゴリー化を行う。アメーバでさえも、出会う物に対して近づくか離れるかで、食べられる物か食べられられない物のどちらかにカテゴリー化する。アメーバにはカテゴリー化をするかしないかという選択は与えられていない。カテゴリー化とはせずにはいられないものである。同じことは、動物世界のどのレベルにおいても当てはまる。動物は、食物、捕食者、配偶者候補、同じ種の仲間、などをカテゴリー化する。動物のカテゴリー化は、それぞれの動物の感覚器官、運動能力、対象を操作する能力により決まってゆく。
Evey living being categorizes. Even the amoeba categorizes the things it encounters into food or nonfood, what it moves toward or moves away from. The amoeba cannot choose whether to categorize; it just does. The same is true at evey level of the animal world. Animals categorize food, predators, possible mates, members of their own species, and so on. How animals categorize depends upon their sensing apparatus and their ability to move themselves and to manipulate objectcs. (p. 17)
著者は続けてこう言います。
生き物はカテゴリー化せざるを得ない。我々は神経機構を備えた存在であり、私たちのカテゴリーの形成は、私たちがどのように身体化されているかによって決まる。このことが意味することは、私たちが形成するカテゴリーは、私たちの経験の一部であるということである。カテゴリーとは、私たちの経験を、認識可能な種類に差異化する構造である。したがってカテゴリー化とは、経験という事実の後で生じる、純粋に理知的なことでない。そうではなく、カテゴリーを形成し使用することは、経験そのものの素材なのである。カテゴリーの形成と使用には、私たちの身体と脳が常に関わっている。一部の瞑想的伝統文化は、私たちが自らのカテゴリーを「超越」し、カテゴリー化以前で概念化されていない純粋な経験を得ることができるとしているが、そんなことは私たちにはできない。神経機構を備えた存在にそのようなことはできない。
Living systems must categorize. Since we are neural beings, our categories are formed through our embodiment. What that means is that the categories we form are part of our experience! They are the structures that differentiate aspects of our experience into discernible kinds. Categorization is thus not a purely intellectual matter, occuring after the fact of experience. Rather, the formation and use of categories is the stuff of experience. It is part of what our bodies and brains are constantly engaged in. We cannot, as some meditative traditions suggest, "get beyond" our categories and have a purely uncategorized and unconceptualized experience. Neural beings cannot do that. (p. 19)
カテゴリー化とは、私たちの身体と脳が行なっていることの一部ですが、私たちの身体はこの世界で動きまわり、私たちの脳はその運動について表象するわけですから、身体によって形成されたカテゴリーとは、感覚運動的 (sensorimotor) なものと言えます。心を考える際に、私たちは私たちがいかにこの世界で動いているかということを考える必要があります。
身体により形成された概念は、神経機構の一つの構造であり、それは実際に私たちの脳の感覚運動システムの一部であるか、それを利用しているものである。したがって、概念的推論の多くは、感覚運動的推論なのである。
An embodied concept is a neural structure that is actually part of, or makes use of, the sensorimotor systems of our brains. Much of conceptual inference is, therefore, sensorimotor inference. (p. 20)
かくして私たちは、独自の身体を持ちそれを使う故にこの世界で形成されるカテゴリーを有しますが、そのうちのいくつかは「基本レベル・カテゴリー」 (basic level categories)と呼ばれます。(基本レベル・カテゴリーに関しては、
レイコフ著『認知意味論』のまとめの「3.1 基本レベル (basic level) 」の項を御覧ください)。
2.2 身体的形成の三つのレベル
カテゴリーの例を通じて、私たちは、「心」や「カテゴリー」や「概念」や「推論」なども「身体的形成」 (embodiment) の帰結であることを見てきましたが、この身体的形成には、現象学的レベル、認知的無意識レベル、神経回路網の身体的形成レベルを認めることができます。著者はこの三つのレベルをどれも落とさずに、これらを相互連関のうちに研究することが必要だと考えています。
(1) 現象学的レベル (phenomenological level)
「現象学的レベル」とは、「意識的あるいは意識に到達できる」レベルのこと( The
phenomelological level is conscious or accessible to conscious. p. 103)で、「クオリア」 (qualia) でもあります。たとえばフッサール (Edmund Husserl)やドレイファス(
Hubert Dreyfus)は、もっぱらこのレベルを研究の対象とするべきだと主張しました(p. 108)
(2) 認知的無意識 (cognitive unconscious)
「認知的無意識」とは、言語理解・使用を含むすべての意識的経験を可能にしている心的作動であり、これらを仮定せず意識の働きだけで私たちは経験を説明することはできません。(It [= The cognitive unconscious] consists of all those mental operations that structure and make possible all conscious experience, including the understanding and use of language. ... That is, the cognitive unconscious is what has to be hypothesized to account for generalizations governing conscious behavior as well as a wide range of uncounscious behavior. p. 103) このレベルを研究のレベルとする代表例としてはチョムスキーやフォーダー (
Jerry Fodor)がいます (p. 108)。
(3)神経回路網の身体的形成 (Neural embodiment)
神経回路網の身体的形成とは、概念や認知的作動の特性を、神経回路網のレベルで示す構造についてのことです。 (
Neural embodiment concerns structures that characterize concepts and cognitive operations at the neural level. p. 102) チャーチランド夫妻 (
Paul Churchland and
Patricia Churchland) は、この神経科学レベルの科学以外は必要なく、その他の学問はやがて消去されるべきだと主張し、消去主義的物質主義者 (eliminative materialists)と呼ばれています。
著者は、これら三つのレベルはそれぞれに私たちの心の働きを説明するのに意義があるので、どれも欠かさずに、相互連関的に研究を進めるべきだとしています。現象学的レベルの研究、認知的無意識レベルの研究と神経回路網レベルの研究は相互否定するべきでなく、互いの知見を参照すべきなのです。著者は次の「概念のメタファー性」で、私たちが意識レベルで経験していることは、実はメタファー的性格という認知的無意識の構造によっていることを示します。そしてその認知的無意識の構造は、私たちの身体のあり方により神経回路網に物理的 (physical)に表現されていることは、これまでのまとめからもご理解いただけるかと思います。三つのレベルは連関しているのです。
3 概念のメタファー性
ここでは、本書冒頭の「抽象概念は、概してメタファーにより構成されている」 (Abstract concepts are largely metaphorical)についての記述をまとめます。抽象概念といった複雑な概念は、以下に説明する「原初的メタファー」が組み合わされたメタファーであるというのが著者の主張です。
3.1 原初的メタファー
それではその「原初的メタファー」(primary metaphor)とはどういうものでしょう。これらの代表例は、Table 4.1 Representative Primary Metaphors (pp. 50-54)に掲載されていますので、ここではその中から原初的メタファーの種類だけを抜き出してみることにしましょう(ここでは翻訳を省きます)。このように私たちは、概念(A)を、感覚運動領域 (sensorimotor domain)である(B)をメタファー(隠喩)にする形 (A is B)で理解しています。例文やその根拠は原著を見ていただければすぐわかりますが、それぞれに考えてみると面白いかとも思います。
Affection Is Warmth, Important Is Big, Happy Is Up, Intimacy Is Closeness, Bad Is Stinky, Difficulties Are Burdens, More Is Up, Categories Are Containers, Similarity Is Closeness, Linear Scales Are Paths, Organization Is Physical Structure, Help Is Support, Time Is Motion, States Are Locations, Change Is Motion, Actions Are Self-Propelled Motions, Purposes Are Destinations, Purposes Are Objects, Causes Are Physical Forces, Relationships Are Enclosures, Control Is Up, Knowing Is Seeing, Understanding Is Grasping, Seeing Is Touching. (pp. 50-54)
これらの原初的メタファーの働きに気づくと、感覚運動的領域の概念、あるいはそれらかと隠喩的に結合された主観的領域の概念なしには、私たちは抽象的概念についてほとんど語れないことがわかります。「愛」の概念について著者は次のように述べます。
物理的な意味での力を使わない愛の概念を想像してほしい。つまり、引力、電力、磁力といった概念を使わない愛である。さらに、結合、狂気、病、魔法、世話、旅、近接性、熱、自分自身を与えること、といった概念なしの愛の概念について想像してほしい。愛を概念化するこれらのメタファーの働きをすべて取り去ってしまうなら、そこにはほとんど何も残っていない。
Imagine a concept of love without physical force -- that is, without attraction, electricity, magnetism -- and without union, madness, illness, magic, nurturance, journeys, closeness, heat, or giving of oneself. Take away all those metaphorical ways of conceptualizing love, and there's not a whole lot left. (p. 82)
3.2 抽象概念をメタファーで分析すると
この本の面白いところは、愛だけでなく、もっと抽象的で基本的であり、私たちにとっては世界の根源的条件として信じて疑わないような概念までもがメタファーの働きにより形成されていることを説明しているところです。ここでは「時間」、「出来事と原因」、「心」についてごくごく短くまとめます。(「自己」、「道徳性」については割愛します)。本書は哲学書として、これらの抽象概念について丁寧に論じていますから、その論考を以下のようにそのごく一部に注目してまとめると誤解を招きかねませんの。ですから繰り返しますが同意なり疑問なり、この本の議論に興味をもった方は必ずこの本をご自身でじっくり読んで下さい。
(1) 時間 (time)
時間に関する概念から、運動や空間や物体などの時間以外の概念を取り除き、この世界での私たちの経験からまったく独立した物(あるいは事(?))として時間を考えることは極めて困難です。著者は次のように論考します。
存在論に関する古典的な問題について考えてみよう。時間は、私たちの心とは独立して存在しているのだろうか。もしそうなら、そのような時間の特性とはどのようなものだろうか。
私たちはこの問題に答えることを拒否する。これは答えようとすれば膠着状態にならざるを得ない問いである。「時間」ということばが名指しているのは、私たちがこの本で記述してきた人間的な概念 -- 出来事間の相関関係やメタファーによって特徴が形成されている概念である。出来事間の相関関係とメタファーが共に私たちの経験を構造化し、私たちは時間を経験する。その経験は、私たちの他の経験と同様に、私たちにとっての現実である。ゆえに、時間とは私たちの身体と脳により「作られた」ものであるが、同時に、その「作られた」時間が、私たちにとっての現実である経験を構造化する。この構造化が、私たちが私たちの世界そしてその世界の物理や歴史について理解をするためには重要なのである。
Consider the classic ontological question: Does time exist independent of minds, and if so, what are its properties?
We reject the question: It is a loaded question. The word time names a human concept of the sort we have described -- partly characterized via the correlation of events and partly characterized via mataphor. Both the correlation of events and the metaphor together structure our experience, giving us temporal experience. That experience, like our other experiences, is real. Thus time is something "created" via our bodies and brains, yet it structures our real experience and allows us an important understanding of our world, its physics, and its history. (p. 167)
(2) 出来事と原因 (events and causes)
出来事や原因などについては、「客観主義」 (objectivism) では不問不動の礎石として考えられています。(客観主義については、
『認知意味論』のまとめと
『心の中の身体』のまとめをご参照ください)。著者は出来事や原因などに関する「客観主義」的見解について次のようにまとめます。
・原因、作用、状態、そして変化に関する私たちの概念は、世界の客観的特徴を表している。これらの概念は、私たちの心とは独立した、実在についての構成物であり、これらが存在するものに関する基礎的存在論の一部をなしている。したがって、原因と結果、作用、状態、そしてに関する概念は、字義通りのものであり、メタファー的なものではない。
・世界の因果的な構造と私たちの因果的推論の特徴を適切に記述する因果関係の論理は、一つだけあり、それは一般的で字義的なものである。
・Our concepts of causes, actions, states, and changes represent objective features of the world; they are mind-independent constituents of reality -- part of the basic ontology of what exists. Hence, the concepts of causastion, action, state, and change are literal, not metaphorical.
・There is a single, general, literal logic of causation that adequately characterizes the causal structure of the world and all of our causal inferences. (p. 171)
しかしながら、西洋哲学は実際のところ、原因を以下のように考えてきました。
原因とは物質的な実体である。
原因とは形式である。
原因とは目的である。
原因とは力または「パワー」を適用することである。
原因とは必要条件である。
原因とは結果より時間的に先立つものである。
原因とは自然法則である。
原因とは自然の一義性である。
原因とは相関もしくは「定常的な共起」である。
Causes are material substance.
Causes are form.
Causes are purposes.
Causes are applications of force or "power".
Causes are necessary conditions.
Causes are temporally prior to effects.
Causes are laws of nature.
Causes are uniformities of nature.
Causes are correlations, or "constatnt conjunctions." (pp. 174-175)
厳密に哲学的に考えても、これだけ多様ですし、社会科学では実際、「道筋」 (causal path)、「ドミノ」 (the domino effect)、「閾値」 (thresholds) 、プレートテクトニクス (the plate tectonic theory of international relations) などを「原因」として記述しています(pp. 172-173)。このような事実からしますと、私たちが有している原因と結果という因果関係の概念については、以下のように総括することが妥当ではないでしょうか。
因果関係に関する私たちの概念そのものが多様である。概念はすべて放射状構造によって構成されており、その中心には人間の行為主体性があり、そこから多くが拡張されている。私たちが因果関係ということばで意味しているのは、これらすべての事例であり、各々の事例にはそれぞれの論理がある。人によってはあるタイプの因果関係を他の因果関係よりも好む場合があるかもしれないが、普通の人々の認知的無意識に関していうならば、どの事例も因果関係としてみなされている。
Our very concept of causation is multivalent: It consists of the entire radial structure, with human agency at the center and many extensions. What we mean by causation is all of those cases with all of their logics. What we take to be the central case is human agency. One might decide that one likes one type of causation better than another, but as far as the cognitive unconscious of ordinary peple is concerned, they all count as causation. (p. 224)
「因果関係」などという科学の礎石のような概念についても、それは人間と無関係に存在する抽象概念というよりは、私たちが人間としての身体をもち、この世界で生活する中で獲得していった原初的メタファーおよびその拡張や結合によって形成した概念と考えるべきではないでしょうか。大きく言ってしまえば、私たちは科学をするにせよ、人間としての科学しかできないわけで、神の目から見たような人間を超えた「真理」の視点からの科学はなしえないわけです(こうしてみるとカントの
「物自体」(Ding an sich, thing-in-itselfの前提は妥当なものと思えてきます)。
(3) 心 (mind)
それでは認知科学や心理学の対象である「心」の概念はどうでしょう。これは客観主義的に解明できる概念なのでしょうか。それとも私たち人間の身体や生活といった要因 --客観主義の信奉者なら「主観的」として罵倒し拒絶する要因-- によって影響を受けている概念なのでしょうか。他の部分のまとめと同様、ここでも結論しか書くことができませんが、心についての私たちの概念を仔細に検討すると、これも多様なメタファーから構成されていることがわかります。以下、それらをリストにします。具体例は本書を参照するか、ご自身でお考えください。
Thinking Is Moving, Thinking Is Perceiving, Thinking Is Object Manipulation, Acquiring Ideas Is Eating, The Thought As Language Metaphor, The Thought As Matematical Calculation Metaphor, The Mind as Machine Metaphor. (pp. 236-247)
英米の分析哲学は、これらのメタファーを洗練化して、心に関して以下のような概念体系を作り出しています。
THE MIND AS BODY
1. Thoughts have a public, objective existence independent of any thinker.
2. Thoughts correspond to things in the world.
3. Rational thought is direct, deliberate, and step-by-step.
THOUGHT AS OBJECT MANIPULATION
4. Thinking is object manipulation.
5. Thoughts are objective. Hence, they are the same for everyone; that is, they are universal.
6. Communicating is sending.
7. The structure of a thought is the structure of an object.
8. Analyzing thoughts is taking apart objects.
THOUGHT AS LANGUAGE
9. Thought has the properties of language.
10. Thought is external and public.
11. The structure of thought is accurately representable as a linear sequence of written symbols of the sort that constitute a written language.
12. Every thought is expressible in language.
THOUGHT AS MATHEMATICAL CALCULATION
13. Just as numbers can be accurately represented by sequences of written symbols, so thoughts can be adequately represented by sequences of written symbols.
14. Just mathematical calculation is mechanical (i.e., algorithmic), so thought is also.
15. Just as there are systematic universal principles of mathematical calculation that work step-by-step, so there are systematic universal principles of reason that work step-by-step.
16. Just as numbers and mathematics are universal, so thoughts and reason are universal.
THE MIND AS MACHINE
17. Each complex thought has a structure imposed by mechanically putting together simple thoughts in a regular, describable, step-by-step fashion. (pp. 248-249)
そういえば
ジュリアン・ジェインズ (
Julian Jaynes)も「意識」(といってもhigher-order consciousnessやextended consciousnessのレベルの意識)は、比喩・アナロジーによってわれわれがその実在を信じるに至ったものだと主張していました。私はかつて彼の意識論のまとめを書きましたが(
Consciousness according to Julian Jaynes)、今度は比喩論として彼の著書である
『神々の沈黙―意識の誕生と文明の興亡』
(
The Origin of Consciousness in the Breakdown of the Bicameral Mind
)を読み直したいと思います(ゆっくり読み書きする時間がほしい・・・)。
ともあれ、「時間」にせよ「原因」にせよ「心」にせよ私たちは通常、抽象概念について問いなおすことをせず、それらを当然の前提としています(さもなければどうして哲学がこれほど多くの人から嫌われているのでしょう!)ですがが、このように哲学的な分析をすると、私たちが学問あるいは科学、すなわち真理・真実(の近似値)として信じて疑わないことにも、固有の特徴があることがわかります。学問・科学には哲学が必要でしょう。
4 思考の無意識性
ここでは「思考は、そのほとんどが無意識的なものである」という本書の主張を、メタファーの働きの説明と絡めながらまとめます。思考のほとんどが無意識であり、かつそれはメタファー的であるというのは、
原初的メタファーの統合理論(The integrated theory of primary metaphors)により説明できます。統合理論は次の4つの部分を持ちます。
(1) ジョンソンの融合理論 (Johnson's theory of conflation): 子どもは、経験の主観的(非-感覚運動的)側面と感覚運動的側面を融合したまま経験し、それらを分離できないため、特定の主観と特定の感覚・運動の連想関係が、その後も続くこととなる (p. 46)。
(2) グレイディの原初的メタファー理論 (Grady's theory of primary metaphor): 原初的メタファーは原子であり、複雑なメタファーを分子として構成する (All complex metaphors are "molecular," made up of "atomic" metaphorical parts called
primary metaphors. p. 46)。しかし付言しておきますと、この「複雑なメタファー/原初的メタファー = 分子/原子」というメタファー(ちょっとややこしいですね)には少し注意が必要です。「原初的メタファー」 (primary metaphors)は、
レイコフの『認知意味論』でいうところの「原子記号」(primitives)ではありません。なぜなら原子記号は、客観主義により内部構造をもたないとされていますが、原初的メタファーには「非-感覚運動的経験が、感覚運動的経験である」という内部構造があるからです。もっとも物理学での「
原子」(atom)も、古代ギリシャ哲学な意味に反して、原子核(陽子と中性子)と電子の内部構造をもっていますので、「原初的メタファーは原子」であるというメタファーに矛盾はないのですが・・・。
(3) ナラヤナンのメタファーの神経理論 (Narayanan's neural theory of metaphor): 非-感覚運動的経験と感覚運動的経験の「融合」あるいは連想関係は、神経回路網で実体化する。 (p. 46)
(4) フォコニエとターナーの概念ブレンディング理論 (
Fouconnier and
Turner's
theory of conceptual blending: 異なる概念領域が共に活性化し、ある一定の条件下では、それらの領域間での結合が形成され、新しい推論がなされるようにもなる(Distinct conceptual domains can be coactivated, and under certain conditions connections across the domains can be formed, leading to new inferences. p. 47)。
これら四つの部分が統合されると以下のことが導き出されます。
四つの部分が一緒になった統合理論は、圧倒的な意味合いをもつ。私たちは幼少期から日常生活世界で普通に行動するだけで、自動的・無意識的にたくさんの原初的メタファー体系を獲得する。ここに選択の余地はない。融合の時期に形成された神経回路網の結合のあり方により、私たちは自然と何百もの原初的メタファーを使って考えるようになる。
The integrated theory -- the four parts together -- has an overwhelming implication: We acquire a large system of primary metaphors automatically and unconsciously simply by functioning in the most ordinary of ways in the everyday world from our earliest years. We have no choice in this. Because of the way neural connections are formed during the period of conflation, we all naturally think using hundreds of primary metaphors. (p. 47)
私たちの思考は、実は幼少期からの心と身体の融合した経験から生じた神経回路上の結合として実体化されたさまざまなメタファー構造の体系に大きな影響を受けており、私たちは通常はこのメタファー的性質を意識しないまま、自動的に思考を形成しているというわけです。だから私たちの思考のほとんどは無意識的であるが、無意識といっても混沌としたものではなく、多くのメタファー構造によって体系づけられているというわけです。
5 認知科学の特徴づけ
このように心の身体的形成 (embodiment) を強調する認知科学は、それまでの認知科学とは明らかに違います。なぜならそれまでの認知科学が前提としていたのは、心の機能だけに注目し心が構成されている媒体の特質は考慮しなくてよいとしていた「
機能主義」(
functionalism) 、知性を「記号操作」 (symbol manipulation)として考える
計算主義 (
Computationalism)、計算主義を支える心的表象 (
mental representation) の考え方(「意味の表象理論」(representational theory of meaning))、人間の認知とは独立した世界の区分法という意味での「古典的
カテゴリー」 (classical
categories)、そしてメタファーを含まない「字義通りの意味」 (literal meaning)だからです (pp. 78-79)。著者はこのような特徴をもつこれまでの認知科学を「第一世代」(the first generation)、身体的形成 (embodiment) の考えに基づく認知科学を「第二世代」(the second generation)と呼び、区別します(参考:
『身体化された心』
(
The Embodied Mind: Cognitive Science and Human Experience
)この本も約20年ぶりに読み返したい!)
第二世代認知科学の特徴は以下のようにまとめられます。
・概念構造は私たちの感覚運動経験およびそれをもたらす神経回路網構造から生じる。私たちの概念システムにおける「構造」の概念そのものが、イメージ図式や運動図式といったものによって特徴づけられている。
・心の構造は、私たちの身体および身体的に形成された経験とつながっているという事実ゆえに本来的に意味を有している。意味を欠いた記号が心の構造を適切に特徴づけることはできない。
・概念には「基本レベル」と呼ばれるものがあるが、これが生じる少なくとも部分的な理由は、私たちの運動図式、ゲシュタルト知覚やイメージ形成の能力である。
・私たちの脳は、感覚運動野から高次の皮質野に活性化パターンを投射するように構造化されている。これらが私たちが原初的メタファーと呼んでいるものを構成している。この種の投射により、私たちは抽象的概念を、身体と直結した感覚運動過程で用いられる推論パターンに基いて概念化することができる。
・概念の構造には、様々なプロトタイプが含まれる:典型的事例、理想的事例、社会的ステレオタイプ、際立った範例、認知的基準点、段階的尺度の終点、悪夢のような事例、などなどである。これらのプロトタイプのそれぞれの種類ではそれぞれ独自の形式の推論が行われている。たいていの概念は、必要十分条件では特徴づけられていない。
・私たちの推論の基本形式が感覚運動的形式もしくはその他の身体に基礎づけられた形式から生じるという点で、理性とは身体的に形成されたものであると言える。
・メタファーによって身体的推論形式が推論の抽象的モードに対応づけられているという点で、理性は想像力に富んだものであると言える。
・概念システムは多元的であり、一元的ではない。典型的には、抽象概念は数多くの概念メタファーによって定義されており、またそれらの概念メタファーはしばしば互いに整合的な関係にはない。
・Conceputual structure arises from our sensorimotor experience and the neural structures that give rise to it. The very notion of "structure" in our conceptual system is characterized by such things as image schemas and motor schemas.
・Mental structures are intrinsically meaningful by virtue of their connection to our bodies and our embodied experience. They cannot be chatacterized adequately by meaningless symbols.
・There is a "basic level" of concepts that arises in part from our motor schemas and our capacities for gestalt perception and image formation.
・Our brains are structured so as to project activation patterns from sensorimotor areas to higher cortical areas. These constitute what we have called primary metaphors. Projections of this kind allow us to conceptualize abstract concepts on the basis of inferential patterns used in sensorimotor processes that are directly tied to the body.
・The structure of concepts includes prototypes of various sorts: typical cases, ideal cases, social stereotypes, salient exemplars, cognitive reference points, end points of graded scales, nightmare cases, and so on. Each type of prototype uses a distinct form of reasoning. Most concepts are not characterized by necessary and sufficient conditions.
・Reason is embodied in that our fundamental forms of inference arise from sensorimotor and other body-based forms of inference.
・Reason is imaginative in that bodily inference forms are mapped onto abstract modes of inference by metaphor. (p. 77)
・Conceptual systems are pluralistic, not monolithic. Typically, abstract concepts are defined by multiple conceptual metaphors, which are often inconsisitent with each other. (p. 78)
管見では、日本の英語教育学はおろか英米の応用言語学でも、「認知科学」あるいは「認知的」(cognitive)という用語を使う場合は、もっぱら第一世代の認知科学的な考えを示しているように思います。しかし、この本が出版されたのが1999年、前述の『
身体化された心
』にいたっては1991年ということを考えれば、私たちも認知における身体性をもっと理解すべきかと思います(ましてや私たちは日本という偉大な身体文化をもつ国に住んでいるのですから!)。
6 西洋的哲学伝統の再検討
こうして私たちの心あるいは認知を、身体の観点から分析してみると、この身体論的分析は西洋哲学、つまりは西洋的教養人の知的基盤そのものの再検討が可能であることがわかります。ここでは本書に扱われているギリシャ哲学、チョムスキー言語学、合理的行動の理論についてごく簡単にまとめます(プラトン、アリストテレス、デカルト、カントおよび分析哲学についてのまとめは割愛します)。
6.1 ギリシャ哲学
西洋文明を理解するには、やはりギリシャ哲学を理解しておく必要があります。ソクラテス以前のギリシャでは以下の様な素朴理論 (folk theory)が広く共有されていました。ギリシャ哲学およびそれ以降の西洋哲学もこの素朴理論の路線を多く継承していますので、ここではそれらを確認しておくことにしましょう。
・世界には体系的な意味があり、私たちはそれに関する知識を獲得することができる。
・特定のモノは、ある一種類のモノに属している。
・すべての存在物には「本質」もしくは「性質」がある。「本質」もしくは「性質」が、ある存在物がその存在であることを可能にし、その存在物の自然な振る舞いの原因ともなっている。
・複数の種類が存在し、それらは本質により規定されている。
・存在するすべてのモノを包括する一つのカテゴリーがある。
・The world makes systematic sense, and we can gain knowledge of it.
・Every particular thing is a kind of thing.
・Every entity has an "essence" or "nature," that is, a collection of properties that makes it the kind of thing it is and that is the causal source of its natural behavior. (p. 347)
・Kinds exist and are defined by essences. (p. 348)
・There is a category of all things that exist. (p. 349)
これら四つの素朴理論 --世界の理解可能性 (Intelligibility of the World)についてのの理論、本質(Essense)についての理論、種類が一般的であること(General Kinds)についての理論、すべてを包括するカテゴリー (All-Inclusive Category)についての理論 (p. 357)-- はそれ以降の西洋哲学とくに形而上学の伝統の基盤になったと著者は説きます。
たとえば
ピタゴラス学派 (
The Pythagoreans)は、存在の本質を物質とする他の哲学者の考え方から一歩進んで、存在の本質は、形式、とりわけ数学的形式にあると考えました。
議論は次のように進む:存在の本質に関する私たちの知識は安定し不変なのもでなければならない。数学的知識こそは、唯一の安定し不変な知識である。ゆえに、存在の本質に関する唯一の知識は数学的知識でなければならない。数学的知識とは数に関する知識である。ゆえに、存在の本質は数である。
The argument goes as follows: Our knowledge of the Essence of Being must be stable and unchanging. Mathematical knowledge is the only stable, unchanging knowledge. Therefore, the only knowledge of the Essence of Being must be mathematical knowledge. Mathematical knowledge is knowledge about number. Therefore, The Essence Of Being Is Number. (p. 361)
私自身、ピタゴラス学派はおろか数学一般について不明ですので臆断は避けなければなりませんが、このような形而上学的信念が、たとえば
「諸行無常」や「諸法無我」、あるいは「色即是空、空即是色」の形而上学的信念とまったく異なることは確かでしょう。後者の形而上学的文化に育ちながら、西洋哲学を学びそれを日本語に翻訳した明治の先達の知的理解力については驚くばかりですが、21世紀に生きる日本の私たちとしては、先達の遺産にあぐらをかいて西洋的形而上学について一知半解なままそれを不動の前提とすることなく、西洋以外の形而上学的伝統について学び直し、私たちの形而上学的理解を再発見するべきだと私は考えます。この本で著者が何度も言うように「好むと好まざるとにかかわらず、私たちは皆、形而上学者である」 (Whether we like it or not, we are all metaphysicians.) (p. 348)からです。
日本の英語教育学界には、欧米の応用言語学学界以上に「数的データを含まない研究は認めない」という頑なな量的研究の信奉者が多いように思います(少なくとも私は何度もそのような匿名査読者に何度も出会ってきましたし、驚くことに最近も出会いました)。そこまでに頑なな方でなくても、教育界においても「数値目標」や「エビデンス」で教育を規定しようとする勢いは非常に強いです。「数字に現れないものもあるんです」と抗弁しても、「まあ、そんなこともあるかもしれないけれど・・・」と、あたかもこの世の人間の営みは数量化できることが当たり前で、数量化できないことは知性の怠慢であるかのごとく語る方もいます(しかしそういった方が数量化に関してきちんと学んでいるかというとそうではない場合がほとんどではないでしょうか。私なりの拙い試みの一つとしては、「
遠山啓『現代数学入門』ちくま学芸文庫」のまとめ記事、あるいは「
英語教育実践支援のためのエビデンスとナラティブ」をご参照下さい)
いや、それよりも「数値目標」や「エビデンス」がないと予算を獲得できないし、うまく「説明責任」を果たせない(=A4で1枚の書類に結果をまとめられない)といったことが本音なのでしょうか。こうなると、背景要因として、標準化されたものの交換をコミュニケーションの基盤とする資本主義社会のあり方にも批判的考察をしなければならないのかもしれませんが(参考:
モイシェ・ポストン著、白井聡/野尻英一監訳(2012/1993)『時間・労働・支配 ― マルクス理論の新地平』筑摩書房)、これ以上話を大きくせずに、話を戻しますと、「量的研究者」の信奉と、その他の種類の研究への不寛容の根源の一つは、こういった西洋的哲学伝統にあると言えるかもしれません(言うまでもなく、この西洋的哲学伝統から、さまざまな流派が出現し、そのうちの一つは
論理実証主義 (
logical positivism)であったりします)。
自らの知的枠組みを反省的に自覚し、上に述べた仏教的文化伝統に根ざしたこの国で、あたかも論理実証主義のように他のアプローチに対して不寛容な態度を敢えてとっているいるのでしたら、それは確信犯ですからまだわかりますし、批判的対話の道も残されています。ですが、そこを無自覚なままに、たかだかここ最近に流行した量的研究方法のみを金科玉条とし、自らの不勉強から、その他のアプローチを学界から排斥するのはやめていただきたく思います(私の経験では、哲学を嫌ったり拒んだりする人に限って、強力な形而上学的信念をもっていたりすることが多いです。そういった方々は自らを問いなおすことが怖いのでしょうか)。
愚痴になりました。再度、閑話休題。
6.2 チョムスキーの哲学
チョムスキーの言語学がデカルトの影響下にあることは、彼自身が著作
『デカルト派言語学―合理主義思想の歴史の一章』
(
Cartesian Linguistics: A Chapter in the History of Rationalist Thought
)で説明する通りですが(参考:
cartesian linguistics (Wikipedia))、レイコフとジョンソンは改めてデカルト哲学の影響を受けたチョムスキーの言語哲学の特徴を、
1. Separation of Mind and Body. 2. Transcendent Autonomous Reason. 3. Essences. 4. Rationality Defines Human Nature. 5. Mathematics as Ideal Reason. 6. Reason as Formal. 7. Thought as Language. Innate Ideas. The Method of Introspectionの7つにまとめていますが(pp. 470-471)、ここではそのうち1と2と6を引用します。
1. 心と身体の分離。 デカルトは、理性、思考、言語の座である心は、身体と存在論的に異なる種類のものであると主張した。心の自律的な働きを説明するのに、身体を参照する必要はないし、また参照するべきでもない。
2. 理性の超越的自律性。 理性は心の活用力であり身体の活用力ではない。理性は自律的である。理性の働きは、理性自身の規則と原則によるものであり、感情、情動、想像力、知覚もしくは運動能力といった身体的なものとはまったく関係がない。
6. 理性の形式性。理性を行使する力とは、心的記号である表象を構造化し関係づける規則にしたがって操作する力である。論理は合理性の活用力の中核そして本質であり、数学こそは、デカルトの論じるところによると、純粋形式の科学なのであるから、思考の理想型である。
1. Seperation of Mind and Body. Descartes claimed that the mind -- the seat of reason, thought, and language -- is ontologically different in kind from the body. One need not, and should not, look to the body for an account of the autonomous workings of the mind.
2. Transcendent Autonomous Reason. Reason is a capacity of mind, not of the body. Reason is autonomous. It works by its own rules and principles, independent of anything bodily, such as feeling, emotion, imagination, perception, or motor capacities. (p. 470)
6. Reason as Formal. The ability to reason is the ability to manipulate representations according to formal rules for structuring and relating these mental symbols. Logic is the core and essence of this rational capacity, and mathematics, Descartes argued, is the ideal version of thought, because it is the science of pure form. (p. 471)
私たちの多くはチョムスキーに倣って、「言語の科学とはかくあるべき」という信念を育んできましたが、それを無批判的に受容あるいは拒絶せずに、哲学的に反省するべきかと思います。「それでは哲学とはどのような営みなのか」と問われるかもしれませんが、それについては後で述べます。
ついでながら述べておきますと、チョムスキーは"mind/brain"という表現を多用しますから、少なくとも脳という身体の一部を扱っていますが、脳はしばしば身体と対立的に考えられている身体の特殊な部位であることは周知のことかと思います。(書きながら思い出しましたが、チョムスキーの2000年の著書である
New Horizons in the Study of Language and Mind
の4章のNaturalism and dualism in the study of language and mindは自然主義と二元論に関するかなり説得力のある議論を呈していたように記憶しています。この章についてはまとめを書き残していませんし、今再読する時間はありませんので、この章・書についてはここに覚書として言及しておくにとどめておきます)。
さらにつけ加えておきますと、チョムスキー言語学の "
Pure Meaningless Syntax: The symbols of a formal language, in themselves, are meaningless. A formal language needs to be interpreted to become meaningful." (p. 473) については、
『認知意味論』のまとめの「2.3 客観主義の帰結」を御覧ください。
このようなチョムスキーの哲学が、認知言語学 (cognitive linguistics)とくに認知意味論 (cognitive semantics) の哲学と大きく異ることはもはや明らかでしょう。認知意味論に関して、著者は以下のように総括します。
・概念が生じ、理解されるのは、身体、脳、世界内の経験を通じてである。概念が意味を得るのは、身体的形成、特に知覚・運動の能力を通じてである。(略)
・概念が、心の想像的側面 --フレーム、メタファー、メトノミー、プロトタイプ、放射状カテゴリー、メンタルスペース、そして概念ブレンデンディング-- を使用していることは重要である。抽象概念は、それよりももっと直接的に身体的に形成された概念(例、知覚・運動概念)をメタファー投射することによりできあがる。(略)
・Concepts arise from, and are understood through, the body, the brain, and experience in the world. Concepts get their meaning through embodiment, especially via perceptual and motor capacities. ...
・Concepts crucially make use of imaginative aspects of mind: frames, metaphor, metonomy, prototypes, radial categories, mental spaces, and conceptual blinding. Abstract concepts arise via metaphorical projections from more directly embodied concepts (e.g., perceptual and motor concepts). ... (p. 497)
「身体、脳、世界内の経験」のつながりについては、最近翻訳書
『現れる存在―脳と身体と世界の再統合』
が出た、
Andy Clarkの
Being There: Putting Brain, Body, and World Together Again
は、まさにこの話題を扱っています。私はこの本も長年本棚に置いたままにしていましたので、翻訳書が出たこの機会に読んでみようと思います(本当に、オイラは読むべき本を読んでいないなぁ、いやマジで)。
ともあれ、デカルト=チョムスキー的な考え方だけが唯一の考え方ではないこと、いや、身体ということをきちんと考えようとすれば、逆にデカルト=チョムスキー的な考え方の方が特殊であることがわかっていただけるかと思います。Andy Clarkの有名な共著論文に"The extended mind"がありますが(参考:
Clark and Chalmers (1998) "The extended mind")、この有名なフレーズにツッコミを入れるなら、「もともとデカルトらが勝手にどこでもない場所に閉じ込めちゃった心を、今更、拡張するなんておたくら西洋人は忙しいねぇ。だいたい単に「お腹が空いた」と言っておけばいいところを、ドイツ語なら "Ich habe Hunger"[=「私」という主語が、「空腹」という対象物(目的語)を所有する]、英語なら"I am hungry" [=「私」という主語が、「空腹」という状態である] なんて表現するから、『"Ich/I"とはなんぞや』なんて問いが重要に思えてくるのさ!」とでもなりましょうか。
そういえばこの本の翻訳者も「心は肉体が生む、ふたつは分離できない、という書物をアメリカ人に書かれてしまったというくやしさみたいなものがある。この考え方はこの国から発信されてもよかった」(翻訳書680ページ)と「訳者あとがき」で述べています。偉大なる身体文化をもつ私たち日本語文化圏の人間は、もっと身体論をきちんと考えて、世界にその知見を発信するべきかと思います(自戒でもあります)。(参考:
Comparing Foreign Language Communication to Budo (Martial Arts),
Do not let mind mind mind (Yes, deconstruction is what Zen is about),
3/4京都講演:「英語教師の成長と『声』」の投影資料と配布資料、
野口三千三氏の身体論・意識論・言語論・近代批判、
竹内敏晴 (1999) 『教師のためのからだとことば考』ちくま学芸文庫など)
6.3 合理的行動の理論 (The theory of rational action)
身体に関する考察も洞察も欠いた、西洋の標準的な形而上学は、哲学好きの閑談を超えて、現実世界にも影響を及ぼしています。それは特に「合理的行動」(rational action)とは何かを規定し、私たちの思考と行動を鋳型にはめてしまう社会科学です ―そう、それは「科学」と呼ばれています!
合理性に関する西洋の古典的見解を著者は以下のように総括します。
1. 合理的思考は字義通りである。
2. 合理的思考は論理的である(形式論理学で定義された専門な意味において)。
3. 合理的思考は意識的である。
4. 合理的思考は超越的、すなわち、脱身体的である。
5. 合理的思考は情熱とは無縁である。
1. Rational thought is literal.
2. Rational thought is logical (in the technical sense defined by formal logic).
3. Rational thought is conscious.
4. Rational thought is transcendent, that is, disembodied.
5. Rational thought is dispassionate.
このリストは、現在、英語教育界でもそのまま使えそうです。つまり
「研究発表や実践報告では比喩的な表現はできるだけ避け、弁証法(参考:Dialectic, Marx's dialectics according to David Harveyなどもちいてはいけません。『直感にしたがって解釈した・行動した』などとは口が裂けても言わず、すべて証拠と根拠に基いて意識的に考え行動したと言いなさい。『身体で感じる』ことや『さまざまな主観』は述べてはいけません。それができないなら、あなたの居場所は学界にありません。学界での居場所が欲しければ、私たちの思考法と行動法にしたがいなさい」というわけです。
実際、社会「科学」を通じて、社会的諸制度は構築されます。「科学」の権威の下、一定の形而上学的信念を疑わずにそこからの思考を発展することを専門とした者は、「専門家」や「学識経験者」として、現行制度の改革を行政権力と共に着手したり、次世代の若者を育てたりします。社会制度は、人間と無関係の自然にもともと存在していたものではありません。私たち人間の考えによってデザインされるものです。「合理的な『現実』の構築」 (The Construction of "Rational" Realities) の節で、合理的選択モデルと市場を例にして著者はこう言います。
手短に言うなら、合理的選択モデルは、私たちの自然な行動の単なる記述ではない。それはむしろ、私たちの規範となり、市場はそのようなモデルがもっとも効果的に使えるように仕立てられている。その結果、多くの企業は合理的選択モデルを使うことで大金を稼ぐ。市場は、このことが可能になるような形で構造化され維持される。
In short, the rational-choice model is not just descriptive of natural behavior; rather, it has been made prescriptive, with markets tailored so that such models can be most effectively used. As a result, many cooperations make a great deal of money using models of rational choice. The market is structured and maintained so that this remains possible. (p. 531)
ある「正しい」とされた思考法と行動法が、学術的お墨付きを得て行政権力となり、その思考法と行動法を万人に強制し、さらには多くの人々がその思考法と行動法を取り入れることこそが賢明なことだと思い始め、人々の営みが大きく変わることは、現在の教育界でも起こっていることでしょう。
ある生活領域を「合理的選択」に合わせることは、私たちの暮らしを、良きにつけ悪しきにつけ、といっても悪い場合の方が圧倒的に多いのだが、ある特定のメタファー複合体の鋳型にはめ込むことを強制することである。その一例が、ビジネスのメタファーを通じて教育を概念化する趨勢、あるいは民営化によって教育を「合理的選択」により経営されるビジネスとしてしまう趨勢である。このメタファーにおいて、生徒は消費者であり、生徒が受ける教育は生産物であり、教師は労働資源である。そうなると知識は商品、すなわち教師から生徒に移譲される市場価値を有したモノとなる。テスト得点が生産物の質となる。よい学校とは、テスト得点が全般に高い学校である。生産力とは、投資金額あたりのテスト得点で測定される。合理的選択理論によって、生産力は最大化されなければならないとする費用対効果分析が必須のものとなる。消費者は、投資金額に対する「最高の教育」を受けるべきなのだ。
このメタファーは何よりも効率性と生産物の品質を強調する。そのことによって教育の現実が隠される。だが、教育はモノではない。活動なのだ。知識は教師から生徒へと文字通り移送されるものではなく、教育は単にある特定の知識の断片を獲得ことではない。教育を通じて、生徒は変わる。生徒が何になるかが重要なのだ。このメタファーは、生徒の役割を無視しているし、生徒の生育や文化全般も無視している。教育者が果たす、非常に手のかかる養育的役割も無視している。さらに、社会に対する多大な貢献に対して適切な報酬を受ける、現在維持されている教育専門職の階級を社会が必要としていることを全面的に無視している。
To bring an area of life into accord with "rational choice" is to force life into the mold of a specific complex of metaphors -- for better or worse, all too often for the worse. An example is the trend to conceptualize education metaphorically as a business, or through privatization to make education a business run by considerations of "rational choice." In this metaphor, students are consumers, their eduation is a product, and teachers are labor resources. Knowledge then becomes a commodity, a thing with market value that can be passed from teacher to student. Test scores measure the quality of the product. Better schools are the ones with higher overall test scores. Productivity is the measure of test scores per doller spent. Rational-choice theory imposes a cost-benefit analysis in which productivity is to be maximized. Consumers should be getting the "best education" for their doller.
This metaphor stresses efficiency and product quality above all else. In doing so, it hides the realities of education. Education is not a thing; it's an activity. Knoweldge is not litrally transmitted from teacher to student, and education is not merely the acquisition of particular bits of knowledge. Through education, students who work at it become something different. It is what they become that is important. This metaphor ignores the student's role, as well as the role of the student's upbringing and the culture at large. It ignores the nurturing role of educators, which often can only be very labor-intensive. And it ignores the overall social necessity for an ongoing, maintained class of education professionals who are apporpriately reimbursed for the immense amount they contribute to society. (p.532)
資本主義が、社会の下部構造を規定するだけでなく、私たちの意識という上部構造までも規定してしまっていることは、マルクスが指摘することですが(参考:
マルクス商品論(『資本論』第一巻第一章)のまとめ)、教育の世界でも資本主義の用語が基礎的な概念メタファーとして使われ、教育の概念を規定してしまっているようです。フレイレはかつて「預金概念でとらえる教育」(Banking concept of education) (参考:
Paulo Freire (1970) Pedagogy of the Opressed)を批判しましたが、生徒を「消費者」扱いし、卒業時の「品質保証」をテスト得点で測定し「説明責任」を果たすという考え方と行動様式は、この日本でも今では堂々と正統なものとして蔓延し、教育管理職の一部はこれらのことばを誇らしげに使っています。
怖いのは多くの人がこういった考え方を「唯一無二の現実」、「科学的で正統な見解」と思い込んでいることです。これらの「現実」はあるメタファー体系を駆使して構築された概念に過ぎないのに。これはチョムスキーも言っていることですが、人間の言語使用の特徴は、条件反射的に状況に固定されていないことです。人間は、自分がどのようなことばを使うかを自己決定できます。私たちは新自由主義の波に巻き込まれ、おそらくは無自覚的に資本主義メタファーを教育の世界でも使い始め、やがてはそのメタファーにより制度となってしまった現実に喘いでいますが、私たちは教育を別様に語ることもできるのです。しかし、その別様の語り方を禁じ、構造的に排除しているのが「学界」だとしたら、それはおそろしく悲しいことですし、また大いなる社会的損失です。私は以前、田尻悟郎先生の語り方を観察していて、田尻先生は教育を工場での製品生産のようには語らず、むしろ自然に近い状態の庭を手入れしている庭師のように語っているのではないかと思い、短いエッセイを
『生徒の心に火をつける―英語教師田尻悟郎の挑戦』
に書きましたが、私はいつかきちんと各種の教育言説に含まれている比喩表現をきちんと比較分析したいと願っています。これは推測ですが、「科学的」とされている学術論文にも、「中立」とされている行政文書にも比喩は多く使われているはずです。なぜなら他人を心底納得させるには比喩の使用が効果的だからです。科学や行政の言語にも哲学的な反省と分析が必要です。
7 哲学とはどうあるべきなのか
それでは「哲学」とはどのような営みなのでしょう。「哲学的な反省と分析」など閑人の戯言ではないでしょうか。著者は、哲学とは言語的意識をもつ動物としての私たちが、良きにつけ悪しきにつけ、行ってしまうことであり、もしそうだとしたら、私たちはよりよく考え、よりよく行動し、よりよく生きるために哲学を行うべきだと考えているように思えます。
私たちは哲学的な動物である。私たちが知る限り、私たちは、なぜ物事がこのように起るのかについて問い、説明することすらできる唯一の動物である。私たちは、自らの存在の意味について深く考え、愛・性・仕事・死・道徳性について常に悩んでいる唯一の動物である。さらに、私たちは、自らの行動を変えるために、自らの生命に対して批判的に反省できる唯一の動物でもあるようだ。
したがって哲学が私たちにとって重要になるのは、第一にそれが私たちの人生の意味を理解させ、私たちがよりよい人生をおくる手助けとなるからである。やるだけの価値がある哲学とは、私たちが何者で、どのように私たちの世界を経験し、どのように生きるべきか、について深い洞察を与えてくれる哲学である。
We are philosophicalo animals. We are the only animals we know of who can ask, and sometimes even explain, why things happen the way they do. We are the only animals who ponder the meaning of their existence and who worry constantly about love, sex, work, death, and morality. And we appear to be the only animals who can reflect critically on their live in order to make changes in how they behave.
Philosophy matters to us, therefore, primarily because it helps us to make sense of our lives and to live better lives. A worthwhile philosophy will be one that gives us deep insight into who we are, how we experience our world, and how we ought to live. (p. 551)
私は本書は、「私たちが何者で、どのように私たちの世界を経験し、どのように生きるべきか、について深い洞察を与えてくれる」哲学の書であり、それが哲学であるがゆえに(認知)科学にもつながる書であると確信しています。このようにまとめを公開して、皆さんにこの本への関心をもってもらおうとする次第です。
科学と哲学の間の関係について著者は次のように述べます。
科学を正直なものにしたいと願うなら、私たちは哲学的洗練を必要とする。これまでの哲学や新たに加わろうとしている哲学をきちんと理解することなしに、科学が自己批判の姿勢を貫くことはできない。 (中略)
他方、哲学はもしそれが責任ある哲学であろうとするのなら、現在行われている関連する科学研究の莫大な成果にきちんと向かい合い理解することなしに、心や言語やその他の人間の生活に関する理論をただ紡ぎだすわけにはいかない。科学との接点がなければ、哲学とは単なるお話であり、人間の身体的形成と認知の現実に依拠していないでっち上げの語りにすぎない。
Philosophical sophistication is necessary if we are to keep science honest. Science cannot maintain a self-critical stance without a serious familiarity with philosophy and alternative philosophies. ...
On the other hand, philosophy, if it is to be responsible, cannot simply spin out theories of mind, language, and other aspects of human life witout seriously encoutering and understanding the massive body of relevant ongoing scientific research. Otherwise, philosophy is just storytelling, a fabrication of narratives ungrounded in the realities of human embodiment and cognition. (p. 552)
科学は哲学を必要とし、哲学は科学を必要とするわけです。しかし、科学や哲学の本の小さな分野のほんの小さな部門の進展についてゆくことさえ難しいのに、私たちが哲学的科学者、科学的哲学者、あるいは哲学者である科学者である人間になることなどできるのでしょうか?私たちは知的に誠実であろうとする限りにおいて、そうあることを目指さねばなりません。もちろんこれはいかなる個人も一人では達成できないことです。科学と哲学は、多種多様で莫大な学術的コミュニケーションを通じて、個々人というレベルではなく人類というレベルで推進するべきことなのでしょう。そして教育という営みに従事する実践者も、可能な限りその科学と哲学のコミュニケーションに耳を傾け、必要に応じてコミュニケーションに参加するべきでしょう。
以上で私のまとめを終わります。以下は蛇足として、私がこの本の読解を通じて考えたことです。
8 雑考
(1) 心を密室から解放する
これまで私たちは、心理言語学や認知科学の教義にしたがって、「心」(mind)を理解するために、心の機能を数量化し、その数字の関係でとらえることを学んできました。「心」は、頭蓋骨の内だけでなく、脳の認知機能の形式的表現(表象)に閉じ込められてきました。いきおい実験も、被験者を一定の認知機能だけに専念させてきました。しかしそれだけが「心」の解明ではないでしょう。「心」を表象から、頭蓋骨から、そして実験室から解放し、心が身体と世界とともに連動する、おそらくは「本来の」と言ってもいい心の姿に戻しましょう。そしてその心-身体-世界(あっさりと「世界内存在」(In-der-Welt-sein,
Being-in-the-World)と呼んだ方がいいのでしょうか)、を他者と出会わせ、共に生活させましょう。それこそが私たちが(少なくとも教育者が)関心をいだく人間であり心でしょう(「
スルメを見てイカがわかるか! 
!」)
(2) 身体経験の重要性
本書の論を信じるなら、私たちの心が「傷つく」という経験・言語表現は、身体的に「傷つく」こととメタファー投射を通じて神経回路網でつながっています。「手を差し伸べる」ことや「支えになる」ことも同様です。それならば「人の心を傷つけることをしてはいけません」という説諭を聞いても、それは身体的な負傷経験を数多くもつ子どもには、それがひょっとしたら文字通りの痛みさえ感じる説諭として聞こえても、身体経験をほとんどもたずに負傷をTVゲーム画面でしか経験したことがない子どもには、何の痛痒も感じない表現に聞こえるかもしれません。
あるいは、現実世界でさまざまな身体経験を積んだ子どもは、その経験に基づく原初的メタファーにより、複雑な抽象概念についてもさまざまに表現できる潜在力をもっていると言えるかもしれません。少なくとも抽象概念の説明のために使われたメタファーを、「腑に落ちる」ように「身体でわかる」度合いは、身体経験の少ない子どもより深いでしょう。また抽象概念の獲得も早いかもしれません。
私は以前、以下の
渋沢栄一に関するエッセイを読んだ時、昔の人の頭の良さは、さまざまな手仕事の知恵を学問・読書と結びつけていたことにあるのかと思いましたが、本書の読書でも、「身体に蓄積された知恵」とでも言うべきものがあるのかと思いました。
渋沢はパリ万博の幕府使節随行員として渡欧していた。その間に大政奉還で幕府は倒れるが、一行はスイス、オランダ、イタリアなども回り、西洋文明の産物、利器を目の当たりにした。
株式組織の産業振興。博物館、動植物園、遊園地、劇場といった文化施設、裁判所から浄水場、舗道に至る公共施設の見事な整備。鮮烈な知的ショックは後に生きる。
実業から福祉、教育にわたる彼の指導、実践と業績は歴史教科書が教えるが、私は未知の状況をきちんと受け止め、発想を転換できる彼の強さに感嘆する。おそらく維新を推し進めた人材はそうした能力の持ち主だったのだ。
現埼玉県の富農に生まれた渋沢は、論語を教わる(これは将来実業人として貫いた理念「道徳経済合一説」になる)一方、13歳から家業である藍玉(あいだま)の商取引を習得した。江戸後期、富農層には思想学問や経済活動が盛んだった。明治維新は下級武士などとともにこうした力が突き上げた。
一時彼は過激な尊王攘夷(そんのうじょうい)派になる。城乗っ取りや、異人館焼き打ちもたくらんだ。断念して仕官したのが1864年。その3年後には欧州で先進文明と制度に驚嘆し、発想の大転換をする。この早さ。
可能にしたのは23歳まで小さな村で家業、学問、読書から身につけた「自家製教養」だと私は考える。勉強は学校でとなった明治以降、実生活にしっかり根を生やした自生型の教養というものを、社会はあまり知らなくなった。
国を開く自家製教養=玉木研二
毎日新聞 2010年10月19日
(3) 「知識」のメタファー性の自覚
「科学的」で「無色透明」のように思える「知識」も、実は存外私たちの身体経験に根ざしたものだったということから、私たちは知識に対して批判的であることを学べるかと思います。先ほど、教育の工場メタファーと庭園メタファーについて語りましたが、私たちはある言説が力をもった時など、「その言説に特徴的なメタファーは何か」、「そのメタファーを採択することにより、物事のどんな側面が強調され、どんな側面が隠されるのか」、「他にはどんなメタファーで語ることが可能か」、「その別のメタファーを使えば、今度はどんな側面が見えてくるか」、と問い、実際に批判的言説分析 (Critical Discourse Analysis)を行うことができます。その批判により、私たちは少なくともその言説に呪縛されることからは免れるでしょう。そして対抗メタファーを使うことにより、物事を多様に見ることを他の人々にも促すことができるでしょう。「知識」はしばしば支配と管理のために使われます。私たちはそういった力に対して自覚的でなければなりません。さもなければことばを操る者により、抵抗もできないまま支配し管理されるだけでしょう。ことばの自覚的な理解と使用により、私たちは力をもつことができます。
(4) 文学的表現の重要性
他人に理解してもらえる多様なメタファーを使いこなせるということは、物事を多元的に捉え、物事の間の諸関連を巧みに見出すということができるということです。こういったメタファーの創造的使用が私たちの力となるということも、上で確認したことでした。こうなりますと、「字義的表現だけを使いなさい」といった(実は実行できない)制約とは無縁の文学的表現 ―もちろん典型的には文学作品に多く見られるが、実はその他の言語使用にも広く見られる、表現に対して自覚的な表現 (参考:
ヤーコブソン関連記事)― 習熟することは、私たちの生きる力につながることがわかります。
「文学なんて非実用的なことを学校で教える必要はない」と言う人が時にいますが、私はこういった人の「実用性」について疑問をもっています。「文学は非実用的」というのは、「工場生産といったそれこそ文字通りの意味のコミュニケーションだけですむ単純作業には要らない」ぐらいの意味であり、工場生産でも単純作業を越え、業務改善や新たな工夫を考案したりする場合には、メタファーを多用したりして、私たちが「文学的表現」と呼ぶ表現を使い始めるのではないでしょうか。あるいは工場の労働条件の改善を求める場合には、経営者とさまざまな形で対話する能力が必要です。ここでも多くのメタファーなどが使われるでしょう。「文学は非実用的であり、学校で教える必要などない」という人は、たとえ自分自身で意識していなくても、学校の役割を、「最小限の読み書きだけできる単純作業労働者の生産である」と主張していることにはならないでしょうか。さらには「単純作業を超えて、労働条件の改善交渉ができるような知性まで教える必要はない」、と言っていることにならないでしょうか。文学的表現は、私たちに世界の新しい可能性を教えてくれます(参考:
野矢茂樹 (2006) 『ウィトゲンシュタイン『論理哲学論考』を読む』 (ちくま学芸文庫))。世間一般に「文学作品」として認定されている言語使用だけに限定する必要はありませんが、私たちは文学的な表現について学ぶことの意義を再検討するべきではないでしょうか。
(5) 外国語教育での機械的直訳主義の批判
英単語とその訳語を対にして丸暗記する学習法は昔から盛んですが、私はそのように単純で機械的な対連合学習は、使用領域が極めて限定された一部の専門用語を除いて、一般的な言語学習としては避けるべきではないかと昔から考えています。少なくとも私が英文の意味を尋ねた時に、学生さんが頓珍漢なことをいう場合の多くで、学生さんが「バ○の一つ覚え」のように唱えている直訳語が、英文理解の邪魔となっていることがあります。または学生さんが英語を話せない時も多くの場合、学生さんはとりあえず思いついた日本語の英訳語が浮かばないことで思考が止まってしまっていたりします。
機械的に訳語を覚えて、そればかりを振り回して外国語を理解・使用しようとすることをここで仮に「機械的直訳主義」と呼ぶことにしますと、機械的直訳主義では、外国語を外国語に即して考えることが阻害されますから、その外国語表現に存在しているメタファーなども、直訳によってしばしば失われ、外国語のメタファー体系を学ぶことができなくなってしまいます。機械的直訳主義は、外国語習得にとって逆効果でないかと私は思っています。
しかし機械的直訳を否定するからといって、私は「翻訳」までも否定しているわけではありません。
「オメの考えなんざどうでもいいから、英文が意味していることをきっちり表現してくれ」でも書きましたが、機械的直訳(あるいは「作業としての機械的英文和訳」と「忠実な英文読解に基づいた創造的日本語表現としての翻訳」はまったく異なるものです。私は機械的直訳主義は排すべきですが、「翻訳」は高度な言語教育として外国語教育の一部に組み込むべきだと考えています。(参考:
山岡洋一さん追悼シンポジウム報告、および「翻訳」「英文和訳」「英文解釈」の区別)
(6) 研究の多元主義
英語教育界の(少なくとも一部の人の)狭量と不寛容そして学界権力の専有については、上で愚痴を言いましたが、量的研究しか英語教育研究として認めないという一元主義による独裁的体制は、その狭量は人々の既得権益のためにはなっても、社会一般のためにはまったくならない行いだと私は考えます。本書が明らかにしているように(どうぞ、上の簡単なまとめだけを本書の内容と勘違いなさらないように!)、私たちは思考において様々なメタファーを使っています。どのメタファーを重要な概念メタファーとして使うかによって、論考は大きく異なってきます。「真理」を「数的に表現できる形式」とする考え方も、一つの考え方、メタファーにすぎません。もちろん多くを厳密に数量化する方法はテクノロジーに最適で、人間はこの思考法で多くの近代的技術を発達させることができましたが、
「近代の技術的発想が人間をそのまま幸福にするものか」、あるいは
「人間は他の人間を単なる技術的操作の対象とだけ考えていいのか」、については慎重に考えなければなりません(カント(
『道徳形而上学の基礎づけ』
)なら後者の問いに否と答えるでしょう)。数量化による技術的発想には明らかな限界があります。ですから量的研究を「教育」研究の唯一の研究法とし、他のアプローチを排斥するのは明らかに間違っています。
それならば"Anything goes"(何でもあり)の相対主義でいいのかとなれば、明らかにそうではいけません。相互無関心で、社会に対して無責任な相対主義(「まあ、これが私の研究ですから口出ししないでくれますか。私もあなたの研究に口出ししませんから)がよい研究体制だとは誰も思わないと思います(しかし過度の専門化が進行した学界は、それぞれの蛸壺の中では競争があっても、蛸壺の間では、この悪しき相対主義となりかねません)。悪しき相対主義は避けなければなりません。
ここはやはり多元主義 (pluralism)、つまりは自らの立論に対しての哲学的反省を含んだ研究が多種多様に現れ、研究者が自分の物差しだけでは判断できない他者の研究を相互に読み合い、その読解と反応のコミュニケーションの中から、学界の構成員がそれぞれ判断力を向上させてゆくような体制です。ここでは一つの物差しを機械的に適用するだけで論文の査読ができるようなことにはなりませんが、そもそも研究とは、とくに教育といった人間に関する研究は、機械的で単純なものであるべきではないでしょう。(参考:
Critical Applied Linguistics,
Alternative Approaches to Second Language Acquisition,
The Social Turn in Second Language Acquisition)
(7) 「実証性」と「数量化」はそのまま重なるわけではない
上の論点に重なりますが、私たちは研究において「実証的」(empirical)であることは重視するべきですが、その態度はそのまま「数量化」(quantification)と重ならないことに注意すべきでしょう。"Empirical"の一般的理解として、Merriam-Websterの定義を引用します。
1: originating in or based on observation or experience [empirical data]
2: relying on experience or observation alone often without due regard for system and theory [an empirical basis for the theory]
3: capable of being verified or disproved by observation or experiment [empirical laws]
4: of or relating to empiricism
どの意味でも概して観察(observation)と経験(experience)が"empirical"であるための条件として掲げられています(3では実験、4では哲学上の経験主義(empiricism)への言及がありますが、基本は観察と経験です)。確かに実験では数量化がしばしば使われますが、観察と経験において数量化は必須ではありません。数量化だけが客観性を担保する方法ではありません。このことは次の主張につながってきます。
(8) 「客観主義的客観性」だけが客観性ではない
本書が明らかにしたように、私たちがしばしば唯一の科学的態度として誤解してしまう「客観主義」(objectivism)は、西洋的哲学的伝統の一つの帰結に過ぎず、人間がもちうる(あるいはもつべき)唯一の思考形態ではありません。ましてや量的研究至上主義は、「客観主義」の特殊形態であり、私たちがあまねく認めるべき「客観性」としてはふさわしくありません。
「客観性」(objectivity)は、公的に共有された理解 (publicly shared understanding)に基いて考えることができるというのが、
マーク・ジョンソンの『心の中の身体』での理解でした。この理解は、客観主義や数量化そのものを否定しませんが、それらが時に含意する狭量さを否定するより広い客観性概念です。
あるいは『認知意味論』の301ページで著者は客観性について次のように総括していました。
『認知意味論』のまとめから日本語翻訳だけを再掲します。
第一に、自分の視点から離れ、状況を他の視点から、しかもできるだけ多くの視点から見ること。
第二に、直接的に有意味なもの --基本レベルとイメージ・スキーマ概念-- と、間接的に有意味な概念の区別ができること。
したがって客観的であるためには以下のことが必要である。
- 人にはそれぞれの視点があり、それは単なる信念の集合ではなく、信念が形成される特有の概念システムであることを知ること。
- 人の視点が何であるかを知り、その概念システムがどのようなものであるかも知ること。
- 他の関連性のある視点を複数知り、それらの視点を形成するそれぞれの概念システムを使うことができること。
- 状況を、複数の他の視点から、それぞれの概念システムを使いながら評価できること。
- 生命体としての人間および私たちの環境の一般的性質からして比較的に安定し明確に定義されている概念(例、基本レベルとイメージ・スキーマ概念)を、人間の目的と間接的な理解の仕方によって変化する概念から区別できること。
またフレイレは、同じ様に"objectivism"を批判し、"objectvity"を"subjectivity"との弁証法的関係の中に見出そうとしています。この場合の"objectvity"と"subjectivity"はそれぞれ「客体性」と「主体性」と訳すべきでしょうか。私たちの主体性抜きの客観的世界はありえず("objectivism"の批判)、だからといってこの世界の客体性抜きにそれぞれが勝手に好き勝手を言っていいということにもならず("subjectivism)の批判)、私たちはそれぞれがそれぞれの主体性をもってこの世界という客体性と関係をもっており、その主体性と客体性の両者相伴って初めて成立する弁証法的関係の中に、私たちは客観性(=客体性=objectivity) (および主体性)を見出すことができるというのが彼の主張とまとめられるかもしれません(
Paulo Freire (1970) Pedagogy of the Opressed)。
残念ながら議論は単純ではありません。しかし世界が複合的で、私たちの人生はさらに複合的であるとしたら、どうして私たちの人生に関する教育研究だけが単純でありえましょうか。私たちはobscurantismは避けますが、過度の単純化は避けます。それは反知性的態度だからです。教育研究が反知性的であるというのは私には根本矛盾のように思えます。
以上で本稿を終えますが、私たちはできるだけ多面的に観察し、そして深く考え、そしてその知見をできるだけ明確に語るべきかと思います。繰り返しますが、過度の単純化は、過度の曖昧化同様、知性的態度ではありません。と言いつつ、本稿が本書を過度に単純化してしまったかもしれない可能性を私は恐れます。いつもながら、おそまつ。
関連記事
ジョージ・レイコフ著、池上嘉彦、河上誓作、他訳(1993/1987)『認知意味論 言語から見た人間の心』紀伊国屋書店
http://yanaseyosuke.blogspot.jp/2012/10/19931987.html
マーク・ジョンソン著、菅野盾樹、中村雅之訳(1991/1987)『心の中の身体』紀伊国屋書店
http://yanaseyosuke.blogspot.jp/2012/11/19911987.html
身体性に関しての客観主義と経験基盤主義の対比
http://yanaseyosuke.blogspot.jp/2013/06/blog-post.html







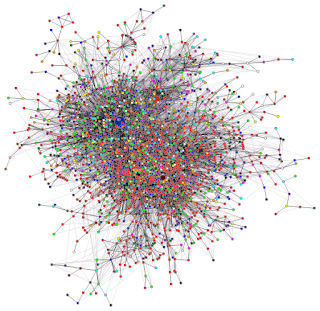.png)









